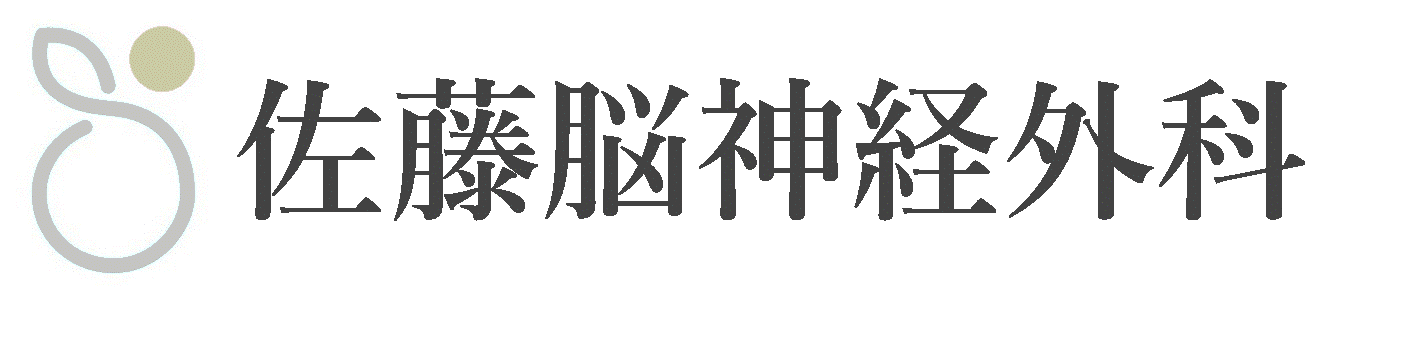脊髄空洞症は、自律神経失調症と診断されがちな病気です。
脊髄空洞症の症状は、体が硬くなったり、手足に力が入らなくなったり、感覚がおかしくなったりします。
診断は、せぼねのMRIを撮影することで、比較的簡単に診断されますが、MRIの検査ができないクリニックでずっと薬の治療を続けている場合もあります。
あまりにも薬が効きにくい神経症状がある場合は、病気の早期発見・早期治療のために、一度MRIを撮影した方が良いです。
有病率│脊髄空洞症は10万人に2人
患者さんの数は、人口10万人あたり、だいたい2人くらいと言われています。
原因│脊髄空洞症は生まれつきの病気
脊髄空洞症は、何も原因なく発症することがほとんどです。
中には、脊髄に腫瘍があって、それが原因となって脊髄空洞症となることもあります。
- 脊髄空洞症を引き起こす病気一覧│医療者向け
-
- 脊髄腫瘍
- 癒着性くも膜炎
- 視神経脊髄炎(ししんけい・せきずいえん)
- 脊髄動静脈ろう
脊髄空洞症の原因
- キアリ奇形Ⅰ型 52%
- 特発性 17%
- キアリ奇形Ⅱ型(二分脊椎・脊髄係留症候群・脊髄髄膜瘤を含む) 9%
- 外傷後癒着性くも膜炎 8%
- 脊髄腫瘍 (上衣腫, 血管芽細胞腫) 5%
- その他 (Dandy-Walker症候群, Klippel- Feil症候群, 水頭症, 感染性疾患, 脱髄・脊髄炎, 頸椎症性脊髄症など) 9%
症状│自律神経失調症と間違えられやすい
脊髄空洞症は、症状がわかりにくく、自律神経失調症と間違えられやすいです。
体が硬くなったり、手足に力が入らなくなったり、感覚がおかしくなったりします。
また、汗がたくさん出たりして、MRIの撮影の前には、いったん『自律神経失調症(じりつしんけい・しっちょうしょう)』の診断がついたりします。
その場合に、脊髄MRIの検査をすると、この脊髄空洞症(せきずい・くうどうしょう)が見つかったりします。
脊髄空洞症の症状
- 痙縮などの錐体路障害による運動障害(59.4%)
- ジャケット型の解離性感覚障害や痛みなどの感覚障害(78.0%)
- 発汗過多、ホルネル徴候、肢肥大などの自律神経障害(23.6%)
- 側弯症などの骨格系症候(30.1%)
- 延髄に空洞が進展していることに起因する脳神経障害(10.3%)
Sudo: Lancet 347 : 1593–1595, 1996
検査│脊髄空洞症はMRIで診断
脊髄空洞症を診断するために、MRIで、『脳』と『せぼね』を撮影します。
せぼねのMRIを撮影して、脊髄(せきずい)という神経の中に水がたまっていたら、この脊髄空洞症を疑います。
脊髄空洞症は、脳の奇形を合併しやすいため、脳のMRIも併せて撮影します。
脳とせぼねのMRIは、1回では撮影できないので、複数回(通常は3回)に分けて撮影します。
治療│脊髄空洞症を根本的に治すのは手術
痛みなどの症状がある脊髄空洞症は、まずは薬で治療しますが、全国的には、最終的に7割くらいの患者さんが手術になっています。
薬の治療は、主に、痛み止め、抗うつ薬、てんかんの薬、などが使われます。
手術は、脊髄の水たまりを抜く手術、合併する脳の奇形を治す手術、脊髄に痛みを緩和する電極を入れる手術(脊髄刺激療法)、などがあります。
- 大後頭孔開放術
- 硬膜減圧術(硬膜外層剥離・硬膜開放)
- 脊髄刺激療法