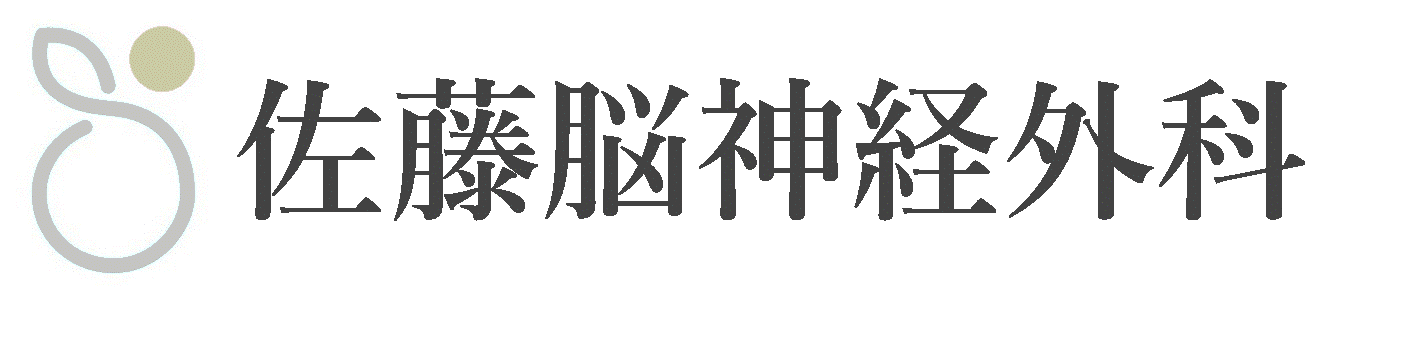糖尿病は、糖尿病予備軍も含めると、全国2000万人を超えます(2016年の統計)。
日本人が1億2000万人とすると、6人に1人が糖尿病ということになります。
糖尿病にかかると、寿命が約10年縮みます。
しかし、糖尿病は今や治療の選択肢が数多く登場しました。
糖尿病は、早期発見・早期治療が最も有効な病気です。
きちんと受診して、きちんと治療しましょう。
糖尿病の治療は、食事療法・運動療法が基本です。 しかし、それでもHbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)が高い場合は、薬を飲むことになります。 それでも糖尿病がコントロール不良の人は、注射を導入します。 注射には、以前はイ[…]
糖尿病とは
糖尿病とは、体の中のインスリン量が少なかったり、インスリンの効きが悪かったりすることが原因で、血糖値が高いままで維持されてしまう病気です。
つまり、インスリン作用が不十分であることが原因で糖尿病が引き起こされます。
体内でのインスリン量が少ないタイプの糖尿病を、『1型糖尿病』と呼びます。
一方で、『体内にインスリンは十分にあるけど、インスリンの効きが悪くなっている』タイプの糖尿病を、『2型糖尿病』と呼びます。
『インスリンの効きが悪くなっている』ことを『インスリン抵抗性』と言います。
- インスリン抵抗性とは
- 『インスリン抵抗性』とは、インスリンの効きが悪くなっている状態を言います。
インスリン抵抗性があると、いろいろな組織のインスリンの反応が良くなく、血糖が下がりにくくなります。
糖尿病の種類
糖尿病の種類は、大きく4つあります。
- 1型糖尿病
- 2型糖尿病
- その他の糖尿病
- 妊娠糖尿病
この中で、暴飲暴食や運動不足などの生活習慣病によって引き起こされる糖尿病は、2型糖尿病と言います。
また、2型糖尿病は、生活習慣病が原因のひとつとなりますが、実際は遺伝的な要素も大きいです。
ですので、同じ食事や同じ運動量でも、糖尿病になる人とならない人がいます。
治療については、後述しますが、1型糖尿病では早々にインスリン注射をしないと血糖が良くならないことも特徴です。
一方、2型糖尿病は、食事制限・運動を行って、生活習慣をまずは直していき、場合によっては飲み薬から始めていきます。
-
1型と2型のタイプ比較
-
糖尿病の型 1型 2型 メカニズム 膵β細胞の破壊 遺伝と環境(過食と運動不足) 家族歴 家系に糖尿病は少ない 家系に糖尿病が多い 発症年齢 小児・思春期に多い 40歳以上で多い 肥満度 関係なし 肥満が多い 自己抗体 あり なし 糖尿病治療ガイド2020-2021より改変
子供の糖尿病
子供の糖尿病は、複数の種類があります。
- 新生児糖尿病
- 1型糖尿病
- 2型糖尿病
- 遺伝性の糖尿病
新生児糖尿病は、生後6ヶ月までに発病することが多いです。
子供の1型糖尿病は、乳児期から発症します。
子供の2型糖尿病は、男女ともに10代前半から発病することが多いです。
遺伝性の糖尿病は、MODYと言い、肥満がなく25歳未満の発症が多いです。
糖尿病の症状
高血糖の症状や、消化器症状、糖尿病が原因で起こる合併症の症状が出ます。
糖尿病が怖いといわれる理由は、この合併症が怖いからです。
糖尿病の合併症には、主に、神経の障害、目の障害、腎臓の障害、があります。
糖尿病にかかると、これらの障害の他に、歯の病気や、精神病や、がんなど、いろいろな病気になりやすいことが知られるようになってきました。
逆に、糖尿病のコントロールが急に悪くなったときは、ガンが身体にできている可能性があり、全身を検索する必要があります。
-
高血糖の症状
-
- 口の乾き
- 水を飲みたくなる
- のどが渇く
- おしっこがよく出る
- 体重が減る
- 疲れやすい
-
糖尿病での消化器症状
-
- 嘔吐
- 下痢
糖尿病が原因でこれらの症状が見られた場合は、『ケトアシドーシス』という、重症の状態が疑われます。
-
糖尿病の合併症を疑う症状
-
- 目が見にくい
- 足がしびれる
- 歩く時に足が痛い
- ED(勃起しにくい)
- 生理がこない
- 汗が出る/出ない
- 便秘
- 下痢
- 足の傷が治らない
-
糖尿病の合併症
- 糖尿病を長年治療していると、細い血管が傷んできて、血流が悪くなることから、神経の障害、目の網膜症、腎臓の機能の悪化、などが起こってきます。
腎臓が悪くなるため、以前から、『糖尿病と言えば、透析になる』というイメージは広く浸透していました。
最近では、『糖尿病は、がんで命を落とす』というイメージに変わってきています。
また、認知症にもなりやすいため、糖尿病はとても怖い病気となってしまいました。
- 神経障害(手足のしびれ)
- 網膜症(眼の病気)
- 腎症(最悪、透析になる)
- 心筋梗塞
- 脳梗塞
- 閉塞性動脈硬化症(足の血管が詰まる)
- がん
- 認知症
- うつ病
- 歯周病
- 骨粗鬆症
- NASH(肝臓の病気)
- 過活動膀胱(頻尿)
- 関節疾患
-
糖尿病は『がん検診』が必須
- 近年、糖尿病による心筋梗塞や脳梗塞は治療の進歩もあり、減少傾向です。
しかし、糖尿病患者さんのガンによる死亡は、34.1%から38.3%に増えています。
糖尿病患者さんのガンは、肺がん、肝臓がん、膵臓がんが多いとされています。
ですので、糖尿病の方は、がん検診は必須です。
検査・診断
病院の血液検査で、血糖が200mg/dL以上、または、ヘモグロビンA1c(エーワンシー)が 6.5% を超えたら、糖尿病の診断となります。
直ちに薬を飲むわけではなく、まずは食事制限・運動を行い、それでもヘモグロビンA1cが上がってくるようであれば、薬の治療となります。
- 血糖 200 mg/dL以上
- HbA1c 6.5% 以上
-
糖尿病の判定基準(医療者向け)
- ①-④ のいずれかが確認された場合は「糖尿病型」と判定します。
別日の再検査で、血糖値に異常があった場合、「糖尿病」と確定診断します。
① 早朝空腹時血糖値126mg/dL以上
② 75gOGTT2時間値200mg/dL以上
③ 随時血糖値*200mg/dL以上
④ HbA1Cが6.5%以上
次の血糖値が確認された場合には、「正常型」と判定。
⑤ 早朝空腹時血糖値110mg/dL未満
⑥ 75gOGTT2時間値140mg/dL未満
上記の「糖尿病型」「正常型」いずれにも属さない場合は「境界型」と判定します。
日本糖尿病学会 編: 糖尿病治療ガイド2018-2019
-
尿検査で腎臓チェック
- 糖尿病になったら、尿検査を行って、腎臓が傷んできていないかを定期的にチェックします。
特に、尿タンパクやが出ていたら、糖尿病が原因で腎臓の機能が悪くなってきている可能性があります。
そのまま進行すると、透析になる可能性もあります。
定期的に尿検査も受けましょう。
尿タンパクが出る前に、『微量アルブミン』という物質が検出されることもあります。
これは、尿タンパクが出てくる前触れです。
微量アルブミンが出始めたら、腎臓の機能障害が徐々に始まっていると考えます。
-
糖尿病になったら眼科を受診
- 糖尿病になると、目の病気の『網膜症(もうまくしょう)』になりやすいです。
網膜症が進行すると、目の中で出血して失明することがあります。
この目の中の出血を『硝子体出血(しょうしたい・しゅっけつ)』と言います。
これらの目の病気は、糖尿病の治療をすることで予防することができます。
糖尿病の検査は、血糖値とHbA1cが主体ですが、補助的に追加する検査もあります。
- 抗GAD抗体
- グリコアルブミン
- 1,5-AG(アンヒドロ・グルシトール)
- IRI
- Cペプチド(CPR)
抗GAD抗体は特に重要で、陽性であった場合は『1型糖尿病』という重症の特殊な糖尿病の可能性があります。
正常値は 5.0 U/mL未満で、陽性の場合は速やかに糖尿病専門医の受診が望ましいです。
グリコアルブミンは、過去2週間の血糖コントロールの状況を把握するために測ります。
一般に 20%未満であれば、血糖管理は良好です。
血糖管理のめやすとしては、一般的にはHbA1cで十分です。
しかし、慢性的に貧血があり、ヘモグロビンが低いと、HbA1cでは上手に判断できません。
その場合は、グリコアルブミンをHbA1cよりも優先して測ることもあります。
主に、透析中などで貧血(腎臓が悪いと貧血になるため)の場合に、グリコアルブミンを重要視する医療機関もあります。
1,5-AGは、食後高血糖のめやすとして測ります。
HbA1cやグリコアルブミンのように全体の血糖値の平均を見るというよりは、1,5-AGは食後高血糖があるかどうかを見るときに使います。
食後に血糖値を測ることができれば、食後高血糖か知ることができますが、外来通院ではタイミングが合わないことも多いです。
その場合は、1,5-AGを計測し、『1,5-AGが 10 μg/mL以上であれば、食後高血糖に対する管理は良好』と判断します。
ただし、SGLT2阻害薬というタイプの薬(ジャディアンス・カナグルなど)を飲んでいる場合は、1,5-AGは低値となるので、判断はできません。
Cペプチド(CPR)は、インスリンを自分で分泌する量を見ます。
特にインスリン使用中の人で、よく測ります。
Cペプチドは 4 ng/mL 以上でよく分泌されていると考えます。
実際は、血糖値に対するCペプチドの分泌量の方が大切です。
Cペプチド・インデックス(=CPR×100 ÷ 血糖値)が食後2時間でも1.5未満であれば、自分の体からのインスリン分泌が少ないため、インスリン注射の適応となります。
糖尿病の治療
食事療法
糖尿病は、食事療法が基本となります。
- 身長と運動量に合わせてカロリー制限
- 高血圧もある人は、塩分6g未満
- アルコールは1日25gまで
- 食物線維を1日20g以上
- 腎臓が良くない場合は、タンパク制限
- 食事で1番はじめに食べるのは野菜、次におかず、最後に炭水化物
- 早食いは良くない
食事の順番も大切です。
『1番はじめに野菜を食べると食後高血糖が抑えられる』ということは広く知られるようになってきました。
最近では、『2番めに食べるものは、おかずが良い』ということも大切です。
野菜、おかずを食べてから、最後に炭水化物・ご飯・デザート類、とするのが正しい食事の順番です。
運動療法
ジョギングやウォーキングなどの有酸素運動をすることで、インスリンが効きやすい体になります。
ウェイトを使ったレジスタンス運動は、筋肉量を増やすことで、基礎代謝を高め、痩せやすい体を作ります。
運動しすぎて、心臓の病気(狭心症・心筋梗塞)を発症しないように、心臓の状態を知っておくことも大切です。
薬物治療
飲み薬と注射薬があります。
いずれも、それぞれ特徴あり、太っている人に効きやすい薬、やせやすい薬、同時には使えない薬、腎臓などの臓器が傷んでいるときは使えない薬、などがあります。
注射薬の代表と言えば、以前はインスリンでしたが、今はインスリン以外の注射薬もあり、その方が低血糖の副作用が出にくく、安全に使いやすいです。
糖尿病の治療は、食事療法・運動療法が基本です。 しかし、それでもHbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)が高い場合は、薬を飲むことになります。 それでも糖尿病がコントロール不良の人は、注射を導入します。 注射には、以前はイ[…]
低血糖を避ける治療が重要
低血糖が怖いのは、夜間に突然死するからです。
夜寝ているときに、自覚なく、低血糖による不整脈で命を落としてしまうことがあり得ます。
特に高齢者の場合は、そこそこの血糖管理で良いので、低血糖になりすぎない治療の組み合わせをおすすめしています。